■ 高市首相の医療改革とは
高市早苗首相は、赤字経営に苦しむ医療機関の支援を目的に、診療報酬改定の時期を待たずに経営改善や処遇改善につながる補助金を前倒しで実施する方針を示しました。
これは、医療現場の疲弊や人手不足を踏まえた「早急な支援」として期待されています。
しかし、この支援がどの医療機関を対象にするかが焦点となっています。
現時点では、まずは高度医療を提供している大学病院や大規模医療機関を中心に行われる可能性が高いと見られており、地域医療や慢性期・精神科病院がどの程度支援対象となるのかは今のところ、不透明です。また、人口減少を踏まえ、不要とされる約11万床を削減が言われています。
■ 精神科・認知症医療の現場で起きていること
近年、認知症のBPSD(行動・心理症状)が強く出ている方を、精神科病院が受け入れるケースが増えています。
しかし、その分だけ身体的・介護的ケアの負担は大きく、現場の人手も限界に近い状態です。
本来、身体合併症(高血圧や糖尿病、肥満、皮膚疾患など身体の病気)のある認知症患者は内科的治療も必要ですが、精神科病院では内科体制が十分でない場合もあります。
「とりあえず受け入れ先があるから安心」とは言えないのが実情です。
■ 在宅ケアの限界と“知らないリスク”
在宅医療や介護を推進する流れの中で、家族が抱える負担も増えています。
認知症の行動障害や介護の限界を知らないまま、追い詰められてしまうケースもあり、悲しい事件(介護殺人など)につながることもあります。
「知ること」は守ることにつながります。
在宅ケア・入院・施設の特徴を知り、それぞれの限界を理解したうえで、家族や本人にとってより良い選択をすることがとても大切です。
■ これから必要なのは国民にとって“公平な支援”
医療改革が進む中で、都会とか田舎とか関係なく、どの病院にも光が届くような公平な支援制度が求められている、と思います。
特に、地域医療を支える病院にも手が届くような政策がなければ、医療格差はさらに広がってしまいます。もちろん、不要な病床削減は必要ですが、高度医療の病床も同じように見直していく必要があると考えます。
精神疾患や認知症の方を含め、病院の病床(ベットの数)を減らし、在宅(家や施設)でみていくことをすすめられている現状も知っておいて欲しいです。
■ まとめ
高市首相の「補助金前倒し」は一歩前進だと思います。実現し、早期の対応をしてほしいと思います。
そして、本当に必要としている現場にまで支援が行き届くのかが、今後の大きな課題です。
医療や介護の現場で働く人だけでなく、一般の方も「制度の方向性を知ること」で、将来の自分や家族の選択に備えられます。
知ることは、守ること。
そんな思いで、これからも現場から発信していきたいと思います。


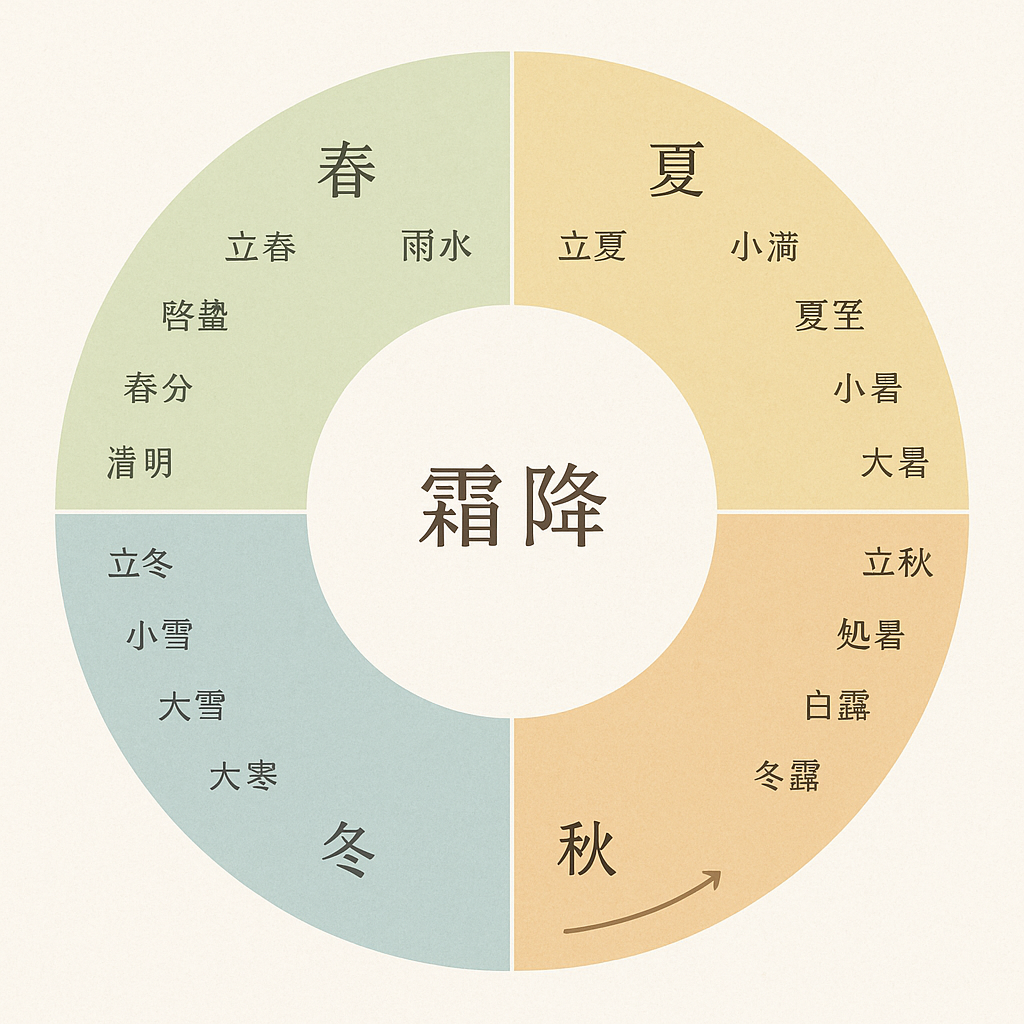
コメント