「もう、点滴もしない方がいいと思うんです。でも、先生には言えなくて……」
ご家族から、そんな言葉を聞くことがあります。
一方で、「何が何でも生き返らせてください」と涙ながらに訴えるご家族もいます。
そのたびに私は、
“本人はどう思っているんだろう”
と考えます。
「食べられない」ことを受け入れるむずかしさ
年齢を重ねたり、認知症の症状が進んだりすると、
「食べる」ことそのものが難しくなっていきます。
頭では理解していても、目の前で食べなくなる姿を見ると、
どうしても「まだできることがあるはず」と思ってしまう。
そんなご家族は少なくありません。
理解と納得は、似ているようでいて違います。
知識として理解していても、
「受け入れる」という心のプロセスには時間がかかるのです。
「本人の思い」はどこにあるのか
日本人には、「家族が察してくれる」「言わなくても分かってくれる」という文化が根強くあります。
けれど、最期の医療において、それが本当に本人の望むかたちにつながっているでしょうか。
本人の思いを確かめないまま、
「家族が決める」「医師が決める」
そんな状況が今も少なくありません。
本人はどうしたいのか。
延命処置を望むのか、それとも自然なかたちで過ごしたいのか。
思いがあっても、言葉にしていなければ、実際には伝わらないのです。
ACP(人生会議)の大切さ
近年、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」という考え方が広まりつつあります。
これは、人生の最終段階において、本人・家族・医療者が話し合い、
どのように過ごしたいかを共有しておく取り組みです。
医師が勝手に決めるのでも、家族だけで抱え込むのでもなく、
本人の意思を中心に考えること。
それが、後悔の少ない選択につながります。
ベストは難しくても、ベターはきっとある
最期の医療に「正解」はありません。
どの選択にも迷いや葛藤があります。
けれど、
本人の思いに寄り添おうとする人がそばにいること、
それだけで救われる命があります。
それが家族であっても、医療者であっても。
「この人はどうしたいんだろう」と想いを向けること。
そこから、より良い最期――“ベターな看取り”が生まれていくのだと思います。

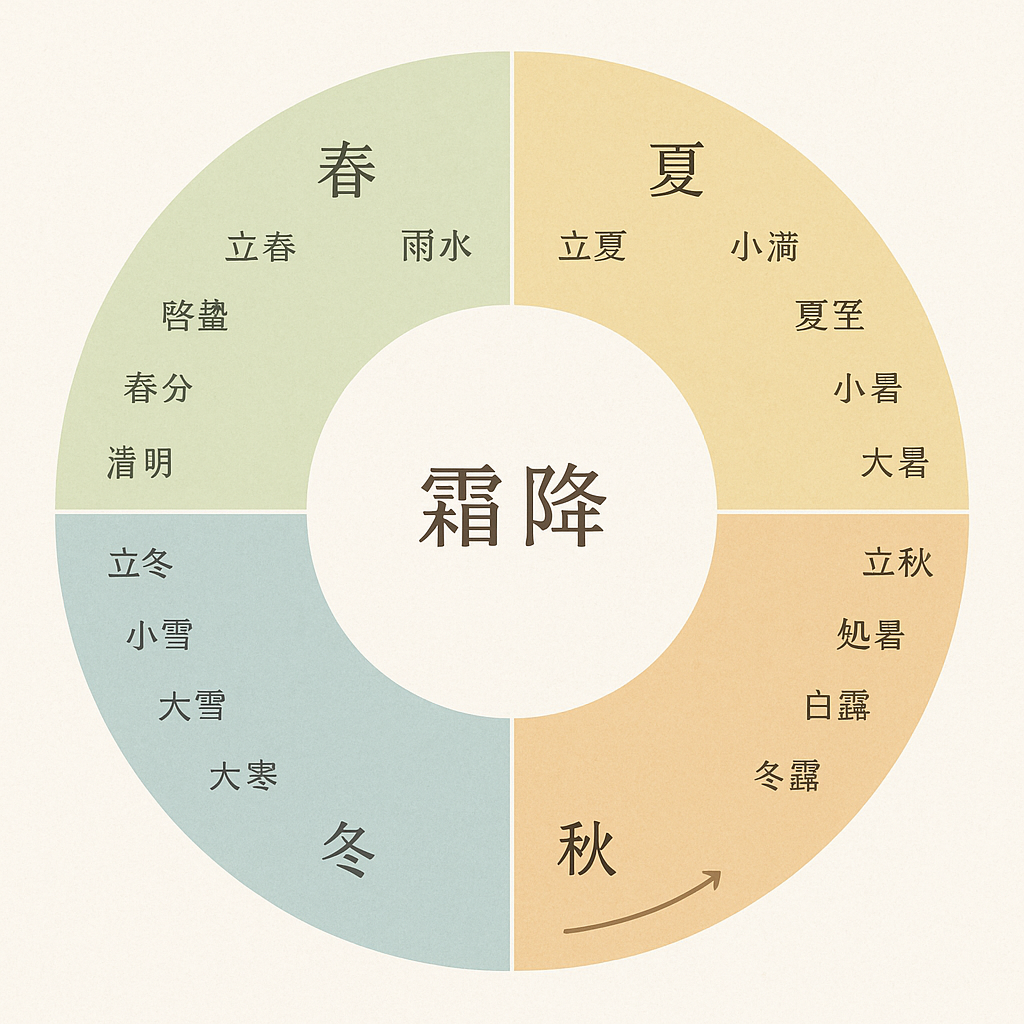

コメント